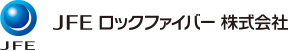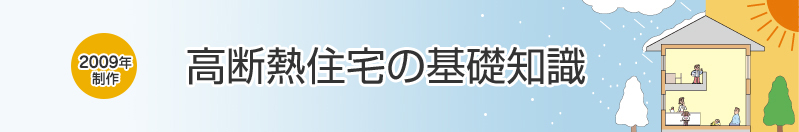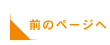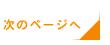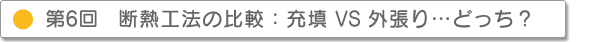
第6回 断熱工法の比較:充填断熱 VS 外張り断熱…どっち?
1-1 工法別断熱部位
「第2回:断熱設計の基本」では部位別の断熱工法を示しました。今回は、工法別に主な断熱部位を確認します。
■ 充填断熱工法
【表 1 充填断熱の断熱部位】
| 天井 | 外壁 | 床 | |
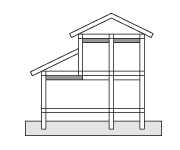 |
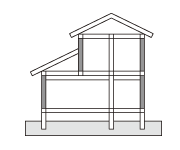 |
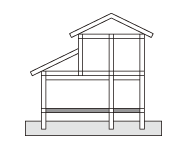 |
|
| 使用 断熱材 |
フェルト状、ばら状の繊維系断熱材の使用が一般的。 | フェルト状の繊維系断熱材が一般的。板状プラスチック系断熱材の使用も可能。吹込断熱工法には、ばら状の繊維系断熱材を用いる。 | フェルト状の繊維系断熱材が一般的。現場発泡断熱材の使用も可能。 |
| 施工法 | 軸組間などの構造空隙に断熱材を施工する。(参照:第2回 P3〜P4) 断熱材の垂れ下がりや隙間が生じないよう施工する(参照:第2回 P2) |
||
■ 外張断熱工法
【表 2 外張断熱の断熱部位】
| 屋根 | 外壁 | 基礎 | |
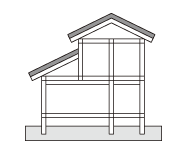 |
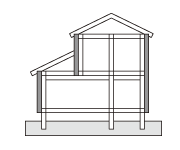 |
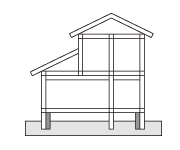 |
|
| 使用 断熱材 |
ボード状のプラスチック系断熱材の使用が一般的 | ボード状のプラスチック系断熱材の使用が一般的 | ボード状のプラスチック系断熱材の使用が一般的 |
| 施工法 | 軸組や構造体の外側に断熱材を施工する。(参照:第2回 P3〜P4) 断熱材は柱や下地に釘などで留めつける。躯体の外側につけるため、外装材等の取り付け強度等に注意が必要である。 |
||
■ 断熱位置による特長−ワンポイントメモ
<断熱位置によるメリット・デメリットを挙げます>
| メリット | デメリット | |
| 充填断熱 天井・床 |
■断熱面積が小さい → 熱ロスが少ない |
■小屋裏と床下が熱的境界の外側である → 小屋裏や床下の空間としての利用が難しい |
| 外張断熱 屋根・基礎 |
■小屋裏と床下が熱的境界の内側にある。 → 小屋裏や床下が空間として利用できる |
■断熱面積が大きい。 → 熱ロスが大きい ■床下が熱的境界の内側である。 → 1階キッチンの床下に食品収納庫を作ると暖まってしまう ■躯体の外側に断熱する。 → ただでさえ狭い庭がより狭くなる |
できるだけ熱ロスを少ない住宅にしようと思ったら、充填・天井断熱がおすすめです。小屋裏をロフト等として利用したいとお考えなら、外張・屋根断熱が良いでしょう。
■ 断熱材による特長−ワンポイントメモ
<断熱材によるメリット・デメリット>
| メリット | デメリット | |
| 充填断熱 天井・床 |
■一般的に繊維系断熱材を使う。 → 材料費が安い → 加工しやすい |
■一般的に繊維系断熱材を使う。 → 別途、防湿・気密のための工事が必要 |
| 外張断熱 屋根・基礎 |
■一般的にボード状プラスチック系断熱材を使う。 → 防湿・気密のための工事が容易 |
■一般的にボード状プラスチック系断熱材を使う。 → 隙間なく施工することが難しい → 材料費が高い |
一般的に充填断熱で使う繊維系断熱材は、別途、防湿や気密のための工事が必要ですが、もともとの断熱材費がプラスチック系断熱材よりも安いことに加えて、断熱面積も少ないので安く上がります。もちろん安かろう悪かろうでないことは、ここまで読んできてくださった方ならおわかりだろうと思います。外張断熱は層構成上、防湿・気密のための措置が容易です。