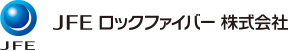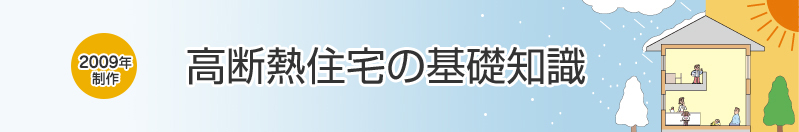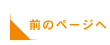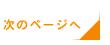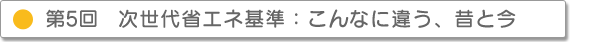
第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今
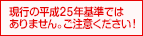
2.省エネ基準とは
2-1 省エネ基準の変遷
「住宅の省エネルギー基準」(通称“省エネ基準”)とは、省エネ法に対応する住宅の性能水準等を詳細に定めた建築主に対する大臣の告示の事です。
1979年の省エネ法制定を受け、1980年(昭和55年)に以下の二つの告示が制定されました。
- 『住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準』(以下、建築主の判断基準と称します)
- 『住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針』(以下、設計・施工指針と称します)
これらの省エネ基準を、通称“旧省エネルギー基準”と称しています(昭和55年基準とも呼ばれています)。旧省エネルギー基準では、気象条件によって全国を5つの地域に区分し、地域ごとに断熱性、日射遮蔽性等に関する基準を規定しました。
その後、省エネ法の改正に連動し、「住宅の省エネルギー基準」は1992年(平成4年)の改正、1999年(平成11年)の全面改正、2001年(平成13年)と2006年(平成18年)の一部改正を行ってきました。
【表 1 省エネ法と住宅の省エネルギー基準の経緯】
| 省エネ法 | 住宅の省エネルギー基準( )は、通称、 住宅性能表示基準省エネ等級で該当する等級を示す |
|
| 1979年 制定 | 1980年[S55] | 住宅の省エネルギー基準の制定(旧省エネルギー基準:等級2) |
| 1993年 改正 | 1992年 [H4] | 住宅の省エネルギー基準改正 (新省エネルギー基準:等級3) ・各構造の断熱性能の強化 ・I地域での気密住宅の適用 |
| 1997年 改正 | 1999年 [H11] | 住宅の省エネルギー基準の全面改正 (次世代省エネルギー基準:等級4) ・躯体断熱性能の強化 ・全地域を対象に気密住宅を前提 ・計画換気、暖房設備等に関する規定の追加 |
| 2001年 | 一部改正 | |
| 2006年 改正 | 2006年 | 一部改正 |
| 2008年 改正 | 2009年 [H21] | 一部改正 |
一部の省エネルギー基準には通称があります。1980年に制定された基準(告示)は“旧省エネルギー基準(又は昭和55年基準)”と呼ばれ、1992年に改正された基準は、“新省エネルギー基準(平成4年基準)”、1999年に改正された基準は、“次世代省エネルギー基準(平成11年基準)”と呼ばれています。
これらの基準では、熱損失係数の判断基準値が規定又は見直され、住宅の断熱性能基準の強化が図られてきました。特に、次世代省エネルギー基準では大幅な断熱性能基準の強化が図られ、住宅の省エネルギー措置に資する多様な手法を公平に評価するとともに、地域の気候条件の特性にきめ細かく配慮したものとなるように基準全体を合理化・詳細化したものとなっています。
また、平成11年には『住宅の品質確保の促進等に関する法律』が制定され、関連して『日本住宅性能表示基準』という大臣の告示が定められました。この告示において「省エネルギー対策等級」が示されています。「住宅の省エネルギー基準」と「省エネルギー対策等級」の関係はおおむね表1のようになります。また、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する【フラット35】、【フラット35】Sの技術基準も省エネルギー基準に準拠しています。このように、住宅の省エネルギー基準は、我が国の住宅の断熱向上による暖冷房負荷と使用エネルギー削減に幅広く活用されています。
【表 2 住宅の省エネルギー基準・省エネルギー対策等級・【フラット35】技術基準の関係】
| 住宅の省エネルギー基準 | 省エネルギー対策等級 | 【フラット35】 技術基準 | |
| 1 | 旧省エネルギー基準(昭和55基準) | 等級2 | 【フラット35】 融資要件 |
| 2 | 新省エネルギー基準(平成4基準) | 等級3 | - |
| 3 | 次世代省エネルギー基準(平成11基準) | 等級4 | 【フラット35】S 融資要件 |