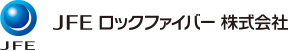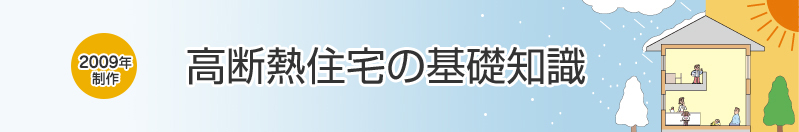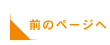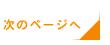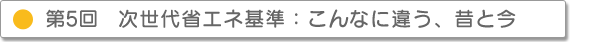
第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今
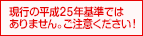
4.住宅事業建築主の判断の基準
今回の省エネ基準改正の目玉と言えるのが「住宅事業建築主の判断の基準」です。
今回の改正は、既に定められている住宅の省エネルギー性能基準を一層強化することを目的とするのではなく、住宅分野の省エネルギー対策の普及と定着を目的にしたものです。そこで、これまで省エネルギー対策の普及が遅れていた建売戸建住宅に対する措置の強化として、「住宅事業建築主の判断の基準」が定められました。
この基準は、これまでに無いユニークなものです。建売戸建住宅は、供給を行う事業主がその断熱性能や設備の性能を設計・建築するものであり、一定の標準仕様に基づいて多数建築されること等を踏まえ、省エネルギー性の向上を促す措置を導入しました。その特徴は、従来の断熱性能の向上に加え、空気調和設備や給湯設備等の建築設備による省エネ効果を加味した点です。また、この基準では、省エネ法第87条第11項の規定に基づき、国土交通大臣から報告を求められた場合に報告する義務があります。(従来の建築主の判断基準では、注文住宅と建売住宅の区別なく“努力義務”でした。この基準では報告が義務として課せられました。)
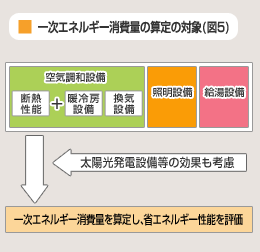
4-1 断熱性能に設備を加味した一次エネルギーによる基準(設備込み基準)
住宅に係る省エネルギー基準によって、近年の家庭におけるエネルギー消費のうち、暖冷房エネルギーは横ばいで推移しています。しかし一方で、照明、家電器具などのエネルギー消費は増加傾向にあります。
「住宅事業建築主の判断の基準」では、省エネルギー性能をより高めることを目的に、従来の断熱性能に加えて、建築設備の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準を定めました。要するに、断熱性能の向上と省エネ設備の導入効果によって、家庭で消費されるエネルギー自体の削減を図ったものです。「建築主の判断基準」が、断熱性能を高めることで暖冷房に要するエネルギーの削減を間接的に図っていることに対し、「住宅事業建築主の判断の基準」は、エネルギーの削減を直接的に行おうとしています。
「住宅事業建築主の判断の基準」では、暖冷房設備と換気設備、照明設備、給湯設備を評価の対象にしています。また、太陽光発電設備については、発電された電力のうち、本基準の対象となる設備に供する電力の一次エネルギー相当量を、住宅の一次エネルギー消費量を削減するものとして評価します。